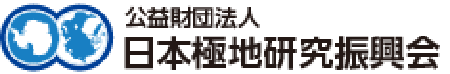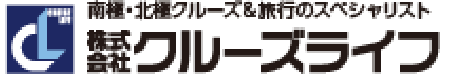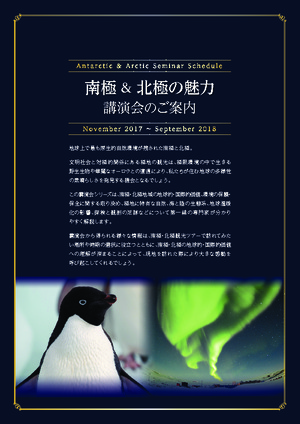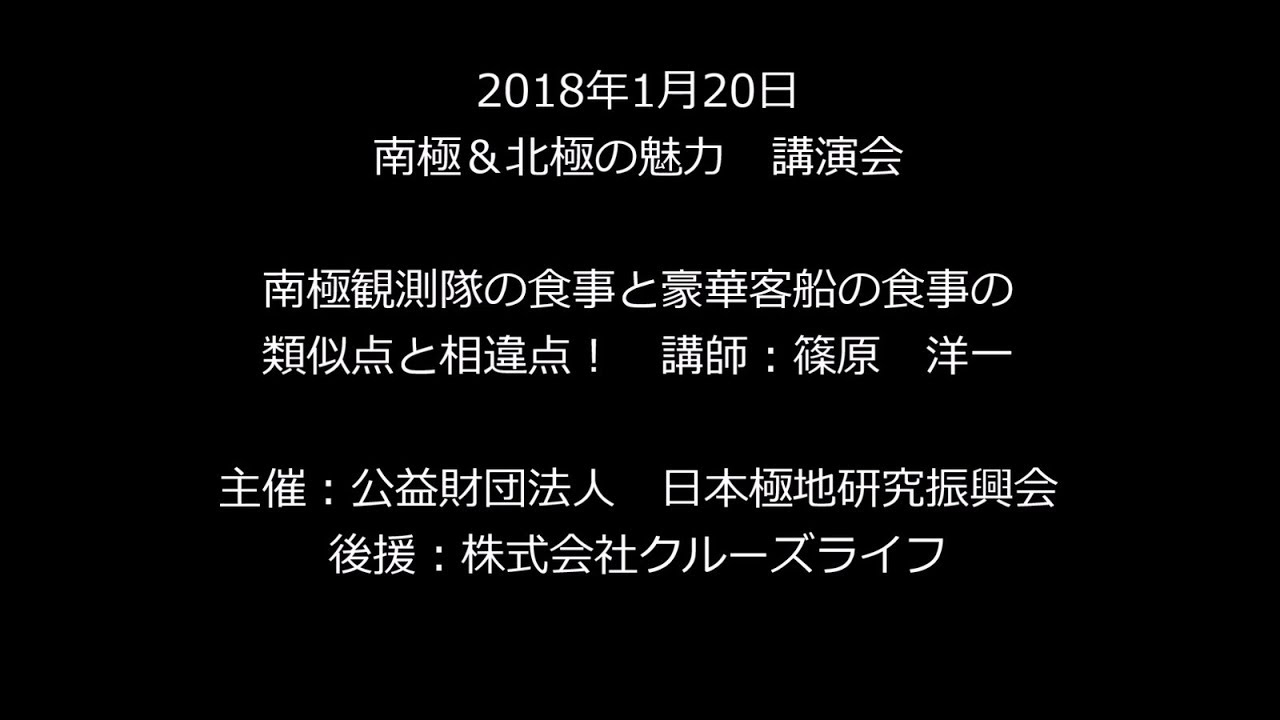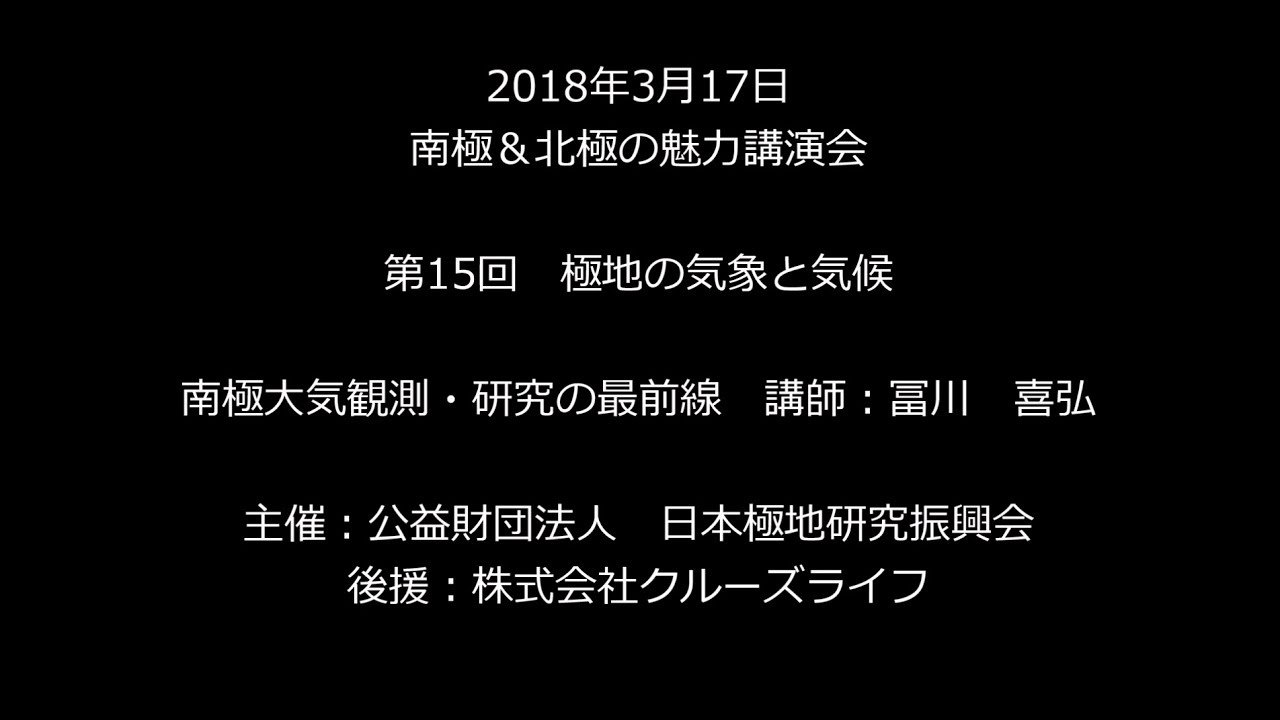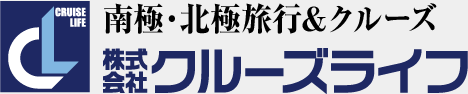南極 & 北極の魅力
講演会 (終了分)
第13回〜第18回
2017年11月〜2018年9月
| テーマ | 開催日 | 講演タイトル | 講師 | |
|---|---|---|---|---|
| 第13回 |
北極から地球環境変動を考える 終了いたしました |
2017年 11月25日 (土) |
変わりゆくグリーンランド~ 犬ぞり猟の旅600kmで見えたもの |
中山 由美 (朝日新聞記者) |
|
グリーンランドで氷を掘って、 過去の気候・環境変動を探る |
東 久美子 (国立極地研究所教授) |
|||
| 第14回 |
南極越冬隊の食事 終了いたしました |
2018年 1月20日 (土) |
女性南極料理人の挑戦 |
渡貫 淳子 (第57次越冬隊) |
|
南極観測隊の食事と豪華客船の 食事の類似点と相違点! 講演内容を動画でご確認いただけます |
篠原 洋一 (第33次、第50次越冬隊) |
|||
| 第15回 |
極地の気象と気候 終了いたしました |
2018年 3月17日 (土) |
南極大気観測・研究の最前線 講演内容を動画でご確認いただけます |
冨川 喜弘 (極地研究所准教授) |
| 地球温暖化の中での南極・北極 講演内容を動画でご確認いただけます |
山内 恭 (国立極地研究所名誉教授) |
|||
| 第16回 |
南極観測隊のしごと 終了いたしました |
2018年 5月19日 (土) |
オーロラ観測と生活 講演内容を動画でご確認いただけます |
源 泰拓 (東京学芸大学 個人研究員) |
| 設営と生活技術の変遷 講演内容を動画でご確認いただけます |
石沢 賢二 (国立極地研究所技術職員) |
|||
| 第17回 |
極地の生き物の不思議 終了いたしました |
2018年 7月7日 (土) |
南極のアデリーペンギンを 追いかける |
塩見 こずえ (国立極地研究所助教) |
|
南極の海氷と動物たち、そして 地球温暖化ー地球の未来 講演内容を動画でご確認いただけます |
内藤 靖彦 (国立極地研究所名誉教授) |
|||
| 第18回 |
オーロラの謎と魅力 終了いたしました |
2018年 9月8日 (土) |
古文書から読み解く江戸時代の オーロラ |
岩橋 清美 (国文学研究資料館准教授) |
| オーロラ観光の魅力 講演内容を動画でご確認いただけます |
福西 浩 (東北大学名誉教授) |
|||
- 第13回 北極から地球環境変動を考える
- 2017年 11月25日 (土) 終了いたしました
- 変わりゆくグリーンランド~
犬ぞり猟の旅600kmで見えたもの講師:中山 由美
(朝日新聞記者) - グリーンランドで氷を掘って、
過去の気候・環境変動を探る講師:東 久美子
(国立極地研究所教授)
- 第14回 南極越冬隊の食事
- 2018年 1月20日 (土) 終了いたしました
- 女性南極料理人の挑戦
講師:渡貫 淳子
(第57次越冬隊) - 南極観測隊の食事と豪華客船の
食事の類似点と相違点!講師:篠原 洋一講演内容を動画でご確認いただけます
(第33次、第50次越冬隊)
- 第15回 極地の気象と気候
- 2018年 3月17日 (土) 終了いたしました
- 南極大気観測・研究の最前線
講師:冨川 喜弘講演内容を動画でご確認いただけます
(極地研究所准教授) - 地球温暖化の中での南極・北極
講師:山内 恭講演内容を動画でご確認いただけます
(国立極地研究所名誉教授)
- 第16回 南極観測隊のしごと
- 2018年 5月19日 (土) 終了いたしました
- オーロラ観測と生活
講師:源 泰拓講演内容を動画でご確認いただけます
(東京学芸大学 個人研究員) - 設営と生活技術の変遷
講師:石沢 賢二講演内容を動画でご確認いただけます
(国立極地研究所技術職員)
- 第17回 極地の生き物の不思議
- 2018年 7月7日 (土) 終了いたしました
- 南極のアデリーペンギンを
追いかける講師:塩見 こずえ
(国立極地研究所助教) - 南極の海氷と動物たち、そして
地球温暖化ー地球の未来講師:内藤 靖彦講演内容を動画でご確認いただけます
(国立極地研究所名誉教授)
- 第18回 オーロラの謎と魅力
- 2018年 9月8日 (土) 終了いたしました
- 古文書から読み解く江戸時代の
オーロラ講師:岩橋 清美
(国文学研究資料館准教授) - オーロラ観光の魅力
講師:福西 浩講演内容を動画でご確認いただけます
(東北大学名誉教授)
講演会講師のご紹介
※ 順不同・敬称略
 中山 由美朝日新聞記者。南極は第45次越冬隊で-60度のドームふじ基地へ、第51次夏隊ではセールロンダーネ山地の氷上で1カ月半暮らし隕石探査を取材。北極はグリーンランドなど頻繁に取材。極地の魅力を新聞、テレビ、講演で発信し続ける“極道 の女”。登山、山スキー、合気道、潜水などアウトドア好きで体力派。
中山 由美朝日新聞記者。南極は第45次越冬隊で-60度のドームふじ基地へ、第51次夏隊ではセールロンダーネ山地の氷上で1カ月半暮らし隕石探査を取材。北極はグリーンランドなど頻繁に取材。極地の魅力を新聞、テレビ、講演で発信し続ける“極道 の女”。登山、山スキー、合気道、潜水などアウトドア好きで体力派。 東 久美子国立極地研究所教授。アイスコア研究センター長。専門は雪氷学で、南北両極のアイスコアの分析による過去の気候・環境変動の研究や、北極域の積雪に含まれるダストや大気汚染物質の研究を実施。グリーンランドや南極でのアイスコア掘削プロジェクトを進める。
東 久美子国立極地研究所教授。アイスコア研究センター長。専門は雪氷学で、南北両極のアイスコアの分析による過去の気候・環境変動の研究や、北極域の積雪に含まれるダストや大気汚染物質の研究を実施。グリーンランドや南極でのアイスコア掘削プロジェクトを進める。 渡貫 淳子第57次南極越冬隊で調理を担当。辻調理師専門学校職員を経て、食彩わたぬき(料理教室及び受注生産のみ)を開業・運営。お店の運営だけではなく、企業のレシピ開発や新規店舗の立ち上げ、TSUTAYAが運営する料理教室(湘南料理塾)の講師も務める。
渡貫 淳子第57次南極越冬隊で調理を担当。辻調理師専門学校職員を経て、食彩わたぬき(料理教室及び受注生産のみ)を開業・運営。お店の運営だけではなく、企業のレシピ開発や新規店舗の立ち上げ、TSUTAYAが運営する料理教室(湘南料理塾)の講師も務める。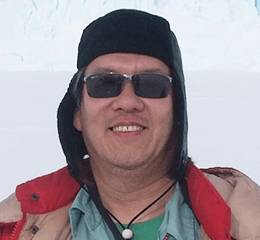 篠原 洋一37年の板前歴で80年~90年までは都内の料亭・割烹等で修業し、91年に第33次南極観測隊、93年から豪華客船「飛鳥」「飛鳥Ⅱ」に和食担当として14年間乗船し世界10周70カ国約200都市を巡り、その後08年に第50次南極観測隊、帰国後横浜「Mirai」を開店し現在に至る。
篠原 洋一37年の板前歴で80年~90年までは都内の料亭・割烹等で修業し、91年に第33次南極観測隊、93年から豪華客船「飛鳥」「飛鳥Ⅱ」に和食担当として14年間乗船し世界10周70カ国約200都市を巡り、その後08年に第50次南極観測隊、帰国後横浜「Mirai」を開店し現在に至る。 冨川 喜弘国立極地研究所宙空圏研究グループ准教授。第53次夏隊、第54次越冬隊に参加し、大型大気レーダー観測やゾンデ観測を担当。専門は大気科学で、対流圏から熱圏までの幅広い高度領域における力学・放射・化学の相互作用や物質輸送に着目した研究を行っている。
冨川 喜弘国立極地研究所宙空圏研究グループ准教授。第53次夏隊、第54次越冬隊に参加し、大型大気レーダー観測やゾンデ観測を担当。専門は大気科学で、対流圏から熱圏までの幅広い高度領域における力学・放射・化学の相互作用や物質輸送に着目した研究を行っている。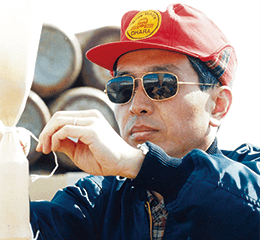 山内 恭国立極地研究所特任教授。専門は気象学で、南極・北極の大気・気候の研究を行っている。北極気候変動研究(GRENE)をリードし、現在は北極域研究推進プロジェクト(ArCS)評議会副議長を務める。南極観測隊には5回参加し、越冬隊長を務める。アメリカの南極点基地にも滞在する。
山内 恭国立極地研究所特任教授。専門は気象学で、南極・北極の大気・気候の研究を行っている。北極気候変動研究(GRENE)をリードし、現在は北極域研究推進プロジェクト(ArCS)評議会副議長を務める。南極観測隊には5回参加し、越冬隊長を務める。アメリカの南極点基地にも滞在する。 石沢 賢二国立極地研究所極地工学研究グループ技術スタッフ。長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。南極観測隊に7回参加(越冬隊5回、夏隊2 回)、越冬隊長を務める。また米国のマクマード基地・南極点基地、 豪州のケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。
石沢 賢二国立極地研究所極地工学研究グループ技術スタッフ。長年にわたり輸送、建築、発電、環境保全などの南極設営業務に携わる。南極観測隊に7回参加(越冬隊5回、夏隊2 回)、越冬隊長を務める。また米国のマクマード基地・南極点基地、 豪州のケーシー基地・マッコ-リー基地等で調査活動を行う。 塩見 こずえ1984年1月生。東京大学大学院農学生命科学研究科・水圏生物科学専攻で博士課程を修了し、2015年より国立極地研究所助教。専門は動物行動学。ペンギン類やミズナギドリ類をはじめとする海鳥を対象にバイオロギング研究を進めている。第59次南極地域観測隊夏隊に参加。
塩見 こずえ1984年1月生。東京大学大学院農学生命科学研究科・水圏生物科学専攻で博士課程を修了し、2015年より国立極地研究所助教。専門は動物行動学。ペンギン類やミズナギドリ類をはじめとする海鳥を対象にバイオロギング研究を進めている。第59次南極地域観測隊夏隊に参加。 内藤 靖彦国立極地研究所名誉教授、南極観測隊に4回参加(越冬3回、夏隊 1回)、越冬隊長を二度務めた。その他、英国、オーストラリア隊にオブザーバーで参加。専門は海洋生態学(ペンギン、アザラシの行動の計測)で、バイオロギングサイエンスの分野の世界的パイオニア。
内藤 靖彦国立極地研究所名誉教授、南極観測隊に4回参加(越冬3回、夏隊 1回)、越冬隊長を二度務めた。その他、英国、オーストラリア隊にオブザーバーで参加。専門は海洋生態学(ペンギン、アザラシの行動の計測)で、バイオロギングサイエンスの分野の世界的パイオニア。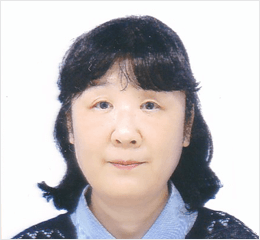 岩橋 清美国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター特任准教授。専門は日本近世史で多摩地域の文化人について研究している。江戸時代のオーロラを文系・理系融合共同研究チームで調べており、オーロラ動態に関する史料を古文書の中から発見した。
岩橋 清美国文学研究資料館古典籍共同研究事業センター特任准教授。専門は日本近世史で多摩地域の文化人について研究している。江戸時代のオーロラを文系・理系融合共同研究チームで調べており、オーロラ動態に関する史料を古文書の中から発見した。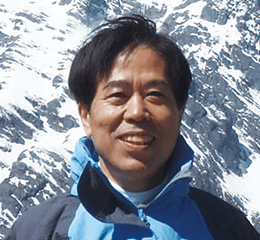 福西 浩公益財団法人日本極地研究振興会・常務理事、東北大学名誉教授。 専門は地球惑星科学で、主に地球や惑星のオーロラ現象を研究している。南極観測隊に4回参加し、 夏隊長や越冬隊長を務める。2007年から4年間、日本学術振興会北京センター長として日中学術交流の発展に尽す。
福西 浩公益財団法人日本極地研究振興会・常務理事、東北大学名誉教授。 専門は地球惑星科学で、主に地球や惑星のオーロラ現象を研究している。南極観測隊に4回参加し、 夏隊長や越冬隊長を務める。2007年から4年間、日本学術振興会北京センター長として日中学術交流の発展に尽す。
パンフレットダウンロード
開催済み講演映像
講演会ページリンク一覧
「南極」について もっと知りたい!
- 南極の氷山、氷河、海氷
- オゾンホール
- 南極大陸
- 秘境「南極」の魅力
- 南極条約
- 南極を訪れる人の手引き
- 講演会のご案内